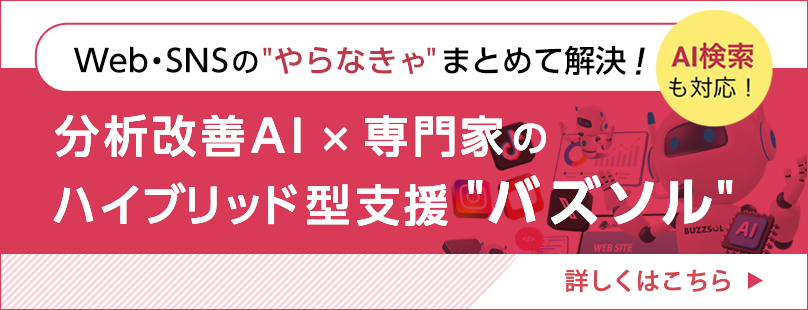著者:ウェブステージ
成果につながるホームページ制作・WEB制作 - ウェブステージ
ウェブステージは、お客様一人ひとりの想いやビジョンを大切にし、ホームページ制作・WEB制作 を通じて理想のカタチを実現いたします。単に見た目の美しさにとどまらず、使いやすさや検索エンジン対策なども考慮し、成果へとつながる設計を心がけています。企業や店舗の信頼性を高めるコーポレートサイトから、集客に強いサービスサイト、ECサイトまで幅広く対応し、目的に合わせた最適なご提案をいたします。制作後も更新や運用サポートを継続し、お客様の事業成長を支えるパートナーとして寄り添います。ウェブステージは、ただ作るのではなく「選ばれるホームページ」をご提供いたします。
ウェブステージ 住所 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2丁目4−1 Tug-Iビル 3F電話 0120-989-963
無料相談・資料請求
クローラがウェブページを収集することを「クロール」といいます。各種検索エンジンはこのクロールされたデータを検索結果に反映させているため、SEOを考えているサイト運営者としては、いつクロールされているのか気になる方も多いのではないでしょうか。
クロール(検索エンジンのWebクローリング)とは
「クローラ」とは、インターネット上のあらゆるリンクをたどってWebサイトなどを検出するプログラムのことです。https://developers.google.com/search/docs/advanced/crawling/overview-google-crawlers
ウェブページはいつクロールされる?
「ウェブページはいつクロールされる?」という疑問に対しての答えですが、結論からいいますと「わからない」というのが実際のところです。
URL検査ツール(旧:Fetch as google)でクロールをリクエスト
いつクローラが巡回するのかは分かりませんが、URL検査ツール(旧:Fetch as google)を使用すれば、こちらからクロールをリクエストすることができます。
重複コンテンツとしてとらえられるとインデックスされないことも
最近では、新しいページをインデックスさせたいため、URL検査ツールでクロールをリクエストしたはずが、インデックスされないという症状も多く聞きます。重複コンテンツと認識されたため、インデックスから外されているのではないか 」と言われています。
ウェブはほぼ無限に近い空間であるため、利用可能な URL をすべて調査してインデックスに登録するとなれば、Google の能力を超えることになります。そのため、Googlebot が 1 つのサイトをクロールできる時間には限界があります。 「大規模なサイト所有者向けのクロールの割り当て管理ガイド」
このためGoogleとしては、限界のあるリソースをうまく動かすために、なるべく余分なページはインデックスしないことが良策です。
つまりこのクロールの効率化が、インデックスされない原因の一つではないかと考えられるわけです。
インデックスされないページがある場合、どこか他のページとの重複がないか調べてみることをおすすめいたします。
「クロール頻度が上がる」=「サイト評価が高まる」ではない
注意したいのは、クロール頻度が上がったからといってサイト評価が高まるわけではない、ということです。確かにクローラは人気のあるサイトや、更新頻度が高いサイトをよく巡回する傾向がありますが、それはインデックス化するためにであって、評価を高めるためにではありません。クロールをリクエストしたとしても、変化のないページだったり、コンテンツパワーが足りないページだったりする場合には、SEOにつながることはほとんどないのです。VIDEO
不安な場合はサイト診断を受けてみましょう
Webステージでは、SEOに強いホームページのコンサルティングと制作を展開しています。メールフォームからはこちら →「問合せフォーム 」へ03-5210-2565 (受付時間 平日9時~18時) SEOに強いホームページ作成ならWebステージ SEO強化のためのホームページ制作プラン コラム記事「いまさら聞けない MFI とは?」
成果につながるホームページ制作・WEB制作 - ウェブステージ
ウェブステージは、お客様一人ひとりの想いやビジョンを大切にし、ホームページ制作・WEB制作 を通じて理想のカタチを実現いたします。単に見た目の美しさにとどまらず、使いやすさや検索エンジン対策なども考慮し、成果へとつながる設計を心がけています。企業や店舗の信頼性を高めるコーポレートサイトから、集客に強いサービスサイト、ECサイトまで幅広く対応し、目的に合わせた最適なご提案をいたします。制作後も更新や運用サポートを継続し、お客様の事業成長を支えるパートナーとして寄り添います。ウェブステージは、ただ作るのではなく「選ばれるホームページ」をご提供いたします。
ウェブステージ 住所 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2丁目4−1 Tug-Iビル 3F電話 0120-989-963
無料相談・資料請求
この記事を書いたメンバー
ウェブステージ集客メンバー。役立つホームページやウェブ活用を研究するウェブステージで、集客に関する情報を配信しています。ホームページを活用した集客戦略が得意分野です。